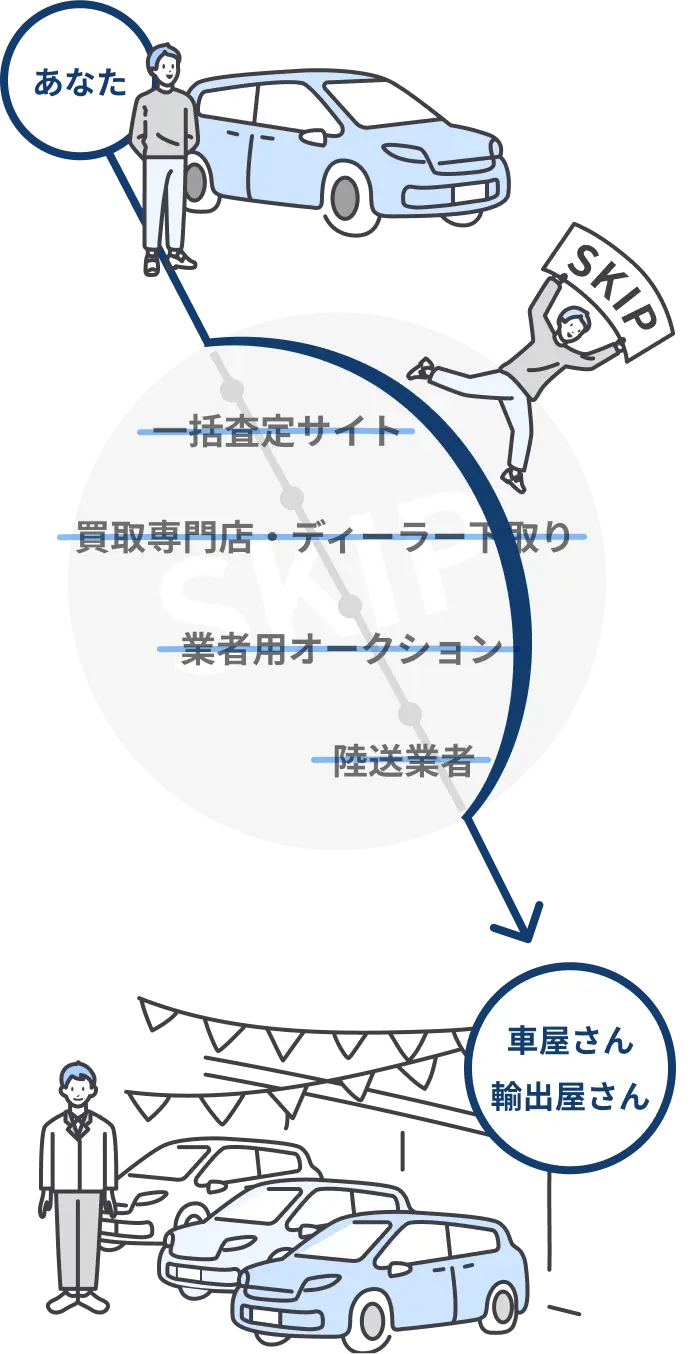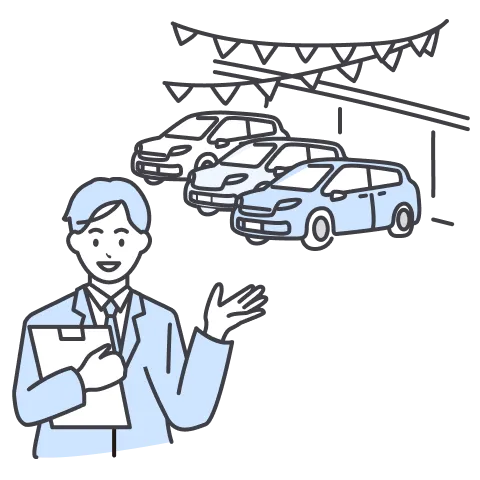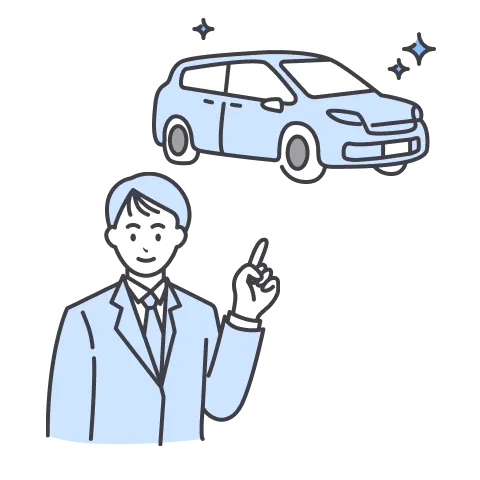登場以来日産を代表するスポーツカーであり続けてきた、フェアレディZ。1969年にダットサン フェアレディの後継として登場し、現在は7世代目(型式的には6世代目と同じなのでビッグマイナーチェンジ扱い)のモデルが販売されているスポーツカーです。2022年の6月に発売した最新の7代目ですが、登場間もなく供給できる数を大幅に上回る受注数となってしまい、あえなく受注を停止。そして2023年8月1日現在でも、受注のストップは改善されていません。なぜここまで人気が出てしまったのでしょうか?
◆7代目Zはどんなクルマ?

まず、この7代目フェアレディZがどんなクルマなのかを見ていきましょう。市販モデルが初公開されたのは、2021年のアメリカ・ニューヨークでした。ここでまず北米仕様が公開され、日本仕様は翌年の1月、東京オートサロンにて発表されました。車両型式「RZ34」が示す通り6代目Z34型と同じ型式となっています。これは、シャシーが変更されていないキャリーオーバーであることを表し、Z34の前に付くRはリファインの頭文字だと言われています。
発表会の場で「史上最高のZを目指した」と開発陣が述べていた、7代目Z。ひと目見てすぐにわかるとおり外観や内装に先代Z34型と共通するところは一切なく、その内容も見れば見るほど先代Z34型とは別モノだと理解できます。実際8割以上のパーツが一新されており、言われなければ絶対にわからないビッグマイナーチェンジだと言えるでしょう。

7代目Zの特徴といえば、筆頭に挙げられるのはそのデザイン。初代フェアレディZ(S30型)を彷彿とさせる、ロングノーズ・ショートデッキのフォルム、丸型に光るヘッドライトユニット、横長の長方形フロントグリル、後ろに向かってなだらかに下がっていくサイドのボディラインなどは、7代目の外観デザイン上で大きな特徴となっています。リアのコンビネーションランプには、4代目(Z32型)をオマージュしたデザインのLEDテールライトが採用されました。

エンジンには、スカイライン 400Rに搭載され話題にもなった、3リッターV6ツインターボのVR30DETTを採用。歴代初の400馬力を達成したところも大きなトピックとなっています。これに組み合わせられるトランスミッションは、6速MTと9速ATが用意されました。先代からホイールベースすら変わっていないシャシーですが、サスペンションはジオメトリー変更や、新設計のモノチューブダンパーを採用するなどして一新。乗り心地のよさと高い操縦安定性を両立させています。
◆需要と供給の均衡がとれるのを待つしかない⁉︎
さて、ここまでザッと車両紹介をしてきただけでも、クルマとして魅力的な存在であることがわかる7代目フェアレディZ。しかし、廉価グレードでも約540万円からという高価な2シータースポーツカーが、なぜ供給が追いつかないほど受注が殺到しているのでしょう。

理由はいくつかありますが、その中でも一番大きな要因だとされていることが、「最後の内燃機関のZ」だということです。ご存知のとおり、日産は世界に先駆けて量産BEVの「リーフ」をリリースするなど、電動化を他社に先駆けて投入してきたメーカーです。しかし、かつて“技術の日産”と呼ばれた時代を知るファンにとっては、ハイパワーなエンジンを積んだスポーツカーこそ憧れの存在であり、フェアレディZはその代表ともいうべき存在でした。初代S30型を知る人にとっては、現代に甦ったS30としても目に映るかもしれません。そんな憧れの存在が、この機会を逃すと確実に電動化されてしまう。そんな懸念を持った人たちが、最後のチャンスを逃さないように求めているのでしょう。

もちろん、純エンジン車としてZ史上初めての400馬力オーバーのモデルとなったことも大きいですし、今や風前の灯火でもあるMT車がラインナップされている点も見逃せません。クルマが好きな人にとっては、魅力的な点が多いクルマなのです。

ただひとつ気をつけたいのは、こういった需要の多さを狙った転売目的の業者も存在しているということです。新車で注文すらできないクルマですから、いま現存しているクルマの価値は非常に高くなります。そういった高価転売を狙った業者が、市場価格を底上げしてしまっているという点も見逃せません。この問題が解決するのは、メーカー側の生産が需要に追いつき、供給量とのバランスが取れた時です。今はその時を待つしか解決方法がないのが悔しいところです。
<文=青山朋弘/写真=日産>